| cover | ||
 |
信州の石仏 | |
| contents | お買い求めはコチラ |
04道祖神私観
道祖神私観

道祖神のもつおもしろさには確かにさまざまな面があるといえる。しかし世の中の多くの人たちは男女間の性的な面にのみ好奇の眼を向けていることに私は大いに不満を感じるのである。いうまでもなく信州の道祖神の中にはそのような好奇心を満足させるものもあるが、道祖神を決してそのような対照のみとして考えることはできないのである。
一般的には何等の先入感ももつことなしに真正面から謙虚に見てもらいたいと思っている。また、わが郷土の人々には今日身近にある道祖神から何かをくみ取って心の糧にして欲しいと思っているのである。
松本博物館の調査によると仏教の渡来以前から信州には道祖神の元祖といわれるものがすでにあったということであるが、これは勿論、原始宗教の形で現われた性器崇拝の思想で、諏訪の尖石遺跡などに見られる長大な石碑をはじめ、各地に残る巨大なシンボルなどそういうものではなかったかと思うのである。しかし原始人たちの大らかな願いや祈りが何等の陰翳なしに、あまりにも堂々と表面に持ち出されたものには変体な好奇心などとまったく関係ない明るさが感じられる。
未だ日本に仏教の渡来する以前にすでに印度には原始仏教としても相当に発達した造型を伴って、道祖神と発生の動機を同じくしたものが現われていたことを知ることができる。現代は芸術の面でもっとも古代に通じているとよくいわれるのであるが、近頃とくに原始美術が問題となってきていて、世界中の古い民族造型がいろいろと発表され、紹介されていることは興味深い。その中で印度の原始仏教であるヒンズー教に男女相愛の姿を表現した「ミトーナ像」のあることは、今日ではあまりに有名である。いわば印度版の道祖神である。それを見ると、印度は東洋の中に入っているが、その感覚はあくまで西方的であり、写実的でありで、むしろギリアャ古代の影響を思わせる人間的なものであるといえよう。造型として素晴らしく、その圧倒的な彫刻は好奇やその意味の趣味からいうならば、とうてい信州の道祖神などは、微温的すぎて問題にはならないであろう。今更ながら千数百年以前にすでにこのように偉大な仏教彫刻を生んだ印度の文化には驚くほかはないのである。
しかし、これはまったく異質の文化であって、造型的にも、内容的にも日本の道祖神とは何等のつながりのないことは明らかである。ただ年代が遠く古いのにわれわれの眼には新しくうつるということは、明治以来欧州的彫刻によって慣らされてきたわれわれの眼がそう感じるだけで、印度では古代の彫刻であることは間違いないのである。だからその新しさは現代の眼で見る縄文・埴輪の造型の純粋な新鮮さとは自ら趣きが違うことがわかる。ここにもわれわれの知らなければならぬことが多い。そこには造型的な歴史の推移の問題がある。
信州の道祖神が男女相愛の姿をとるようになったのは今からせいぜい三、四百年前のことであると思われる。これを世界の歴史から見れば問題にならぬほど新しいことといえる。印度に「ミトーナ」が現われたのは、中国では北魏大同の仏教的造型が見られた時代で、これが日本仏教彫刻ではもっとも古い推古・天平の源流であったはずである。日本の仏教造型のオーソドックスはこれから始まって、藤原・鎌倉期に向かって日本的フォームを形成しつつ徳川の初期にこの信州の道祖神が作られた歴史につながってくるのである。
この道祖神像が一種の仏教的・道教的それと日本神道的な宗教の影響下に生れたことは論をまたないことであろうが、その表現形式はそれらの形を借りながらも、造型の純粋性はまったくユニークな仏像彫刻の世界を示していることである。表現形式の中には当然何等のつながりももたないのに中国の源流にさえ通じるものを感じさせるものがあるのである。
道祖神に現われたユニークな表現と感覚はわれわれにきわめて多くのことを考えさせるのである。約四百年前から始まったと見られる男女相愛の相対像の形式はそれまでの日本に何等かの伝統があったものとも考えられるのではあるが、日本彫刻のモチーフとしては特異なものではないかと思われるのである。発生の動機はミトーナ像と同じものと考えられるものではあるが、異なる民族の異なる内容を示していることは注目しなければならないと思う。道祖神の造型は稚拙ではあるが、あくまでも日本的で、その表現には説明を超えた親近性を感じさせるものが多い。ミトーナ像の様式はあくまで西洋的、ギリシャ的である。
道祖神がその背景にもった世界は民衆に深く浸透した仏教と儒教の戒律時代ではなかったか。男女間の自由な愛情の表現などは、むしろ罪悪視された時代ではなかったか。しかもなおこれを形造った民間の信仰とは如何に根強いものであったのか。社会的には取るに足りぬ草深い僻地の信仰の対象であっても、またそれが卑賤なものであったにせよ、卑俗の中にこそ根強く浸透していた仏教的戒律と矛盾をどのように考えるべきであろうか。よほどの根強い願いであり、祈りでなければ許容されなかったのではなかったか。しかし、徳川の治政が進めば進むほどたとえ表面的にもせよ妥協は余儀なくされたにちがいないのである。それでこそほとんど大部分の道祖神である相愛の男女像は衣冠をつけ、ただ手を握り合い肩を抱くだけの消極的表現にとどまったこともうなずかれるのである。
しかし根強い因襲的思想と封建的家族制度の中で、愛情の表現の自由が束縛されればされるほど、より内面化したことは当然であろう。そこで道祖神の造型的表現は、より多元的な要素をもつにいたったのではなかろうか。これは東洋的に純化されて到達した最終的な洗練の中で他に見られぬユニ-クなものを生み出す原因を作り出したのではなかろうか。また民族のもつ個有の造型力は従来の宗教的芸術形式に束縛されることなく、いっそう内面化することによって一つの時代の独特な文化遺産を残すにいたったものと考えられるのである。あらゆる自由な表現の可能な現代から見れば、あまりに慎しく、微温的な存在でありながら、これを静かに観ればみるほど、ユニークで想像の自由を残すところに芸術の在り方をもういちど考えさせるものがある。


 仕事の失敗DB
仕事の失敗DB
 古典語典
古典語典 シニアビジネスは男がつくる
シニアビジネスは男がつくる 「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負!
「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負! 税理士、そしてコンサルタントとしての生き方
税理士、そしてコンサルタントとしての生き方 江戸歌舞伎と広告
江戸歌舞伎と広告 久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵
久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵 大ノーベル傳
大ノーベル傳 税務調査に強い税理士ご紹介
税務調査に強い税理士ご紹介 TOHO医療に強い税理士紹介センター
TOHO医療に強い税理士紹介センター 東峰書房ショッピングサイト
東峰書房ショッピングサイト 同族会社のための税務調査
同族会社のための税務調査 西洋古典語典
西洋古典語典 東京の季節
東京の季節 ヨーロッパの旅
ヨーロッパの旅 アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践
アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践 かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A
かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A よくわかる医院の開業と経営Q&A
よくわかる医院の開業と経営Q&A クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント
クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント IFRSが世界基準になる理由
IFRSが世界基準になる理由 2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~
2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~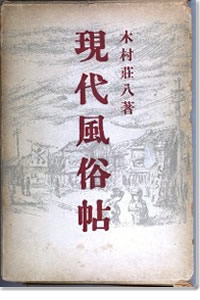 現代風俗帳
現代風俗帳 私のアルコール依存症の記ある医師の告白
私のアルコール依存症の記ある医師の告白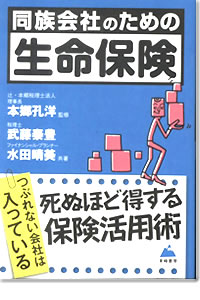 同族会社のための生命保険
同族会社のための生命保険 「税金経営」の時代
「税金経営」の時代 江戸の物売
江戸の物売 江戸の看板
江戸の看板 山麓雑記
山麓雑記 TOHO税務会計メルマガのご案内
TOHO税務会計メルマガのご案内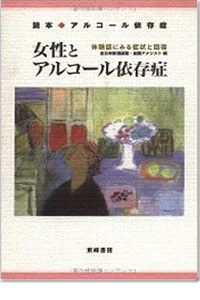 女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復
女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復 版画の歴史
版画の歴史 「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》
「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》 金融マン必携!相続税実践アドバイス
金融マン必携!相続税実践アドバイス 描きかけの油絵
描きかけの油絵 いま、日本にある危機
いま、日本にある危機 「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか?
「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか? 長生きの国を行く
長生きの国を行く 阿蘭陀まんざい
阿蘭陀まんざい 経営ノート
経営ノート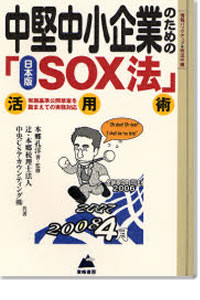 中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術
中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術 グループ法人税務の失敗事例55
グループ法人税務の失敗事例55 バンクーバー朝日
バンクーバー朝日